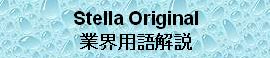 |
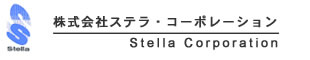 STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月30日
|
|
東北大、九大、古河テクノマテリアル 次世代形状記憶合金の原子配列と原子の動きを観察 東北大学、九州大学、古河テクノマテリアルの共同研究グループは、Cu-Al-Mn系形状記憶合金の原子レベルでの構造変化を解明した。X線吸収分光法(XAS)と第一原理計算(DFT)を用いて、熱処理による合金内部のMn原子の動きやナノスケールの濃度ゆらぎを観測した結果、Mn原子の移動が磁気的性質に影響を受け、形状記憶効果をもたらす規則配列構造の形成を促すことを明らかにした。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月24日
|
|
|
東京エレクトロン 東京エレクトロン宮城の新開発棟が完成
新開発棟は地上3階建て延床面積約4万6,000m2で、プラズマエッチング装置を開発・製造する。投資額は約520億円。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月23日
|
|
芝浦工大とハドラスHD 機能性コーティング剤の共同研究講座「ハドラス機能性薄膜共同研究講座」を開設 芝浦工業大学とハドラスホールディングスは、「ハドラス機能性薄膜共同研究講座」を開設した。共同研究講座は、芝浦工業大学豊洲キャンパス(東京都江東区)に設置。2025年4月1日から2029年3月31日の4年間にわたり、ハドラスのガラス系コーティング技術と芝浦工大の機能性有機ポリマーに関する知見を融合し、新たな有機‐無機ハイブリッドコーティング技術の開発を目指す。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月16日
|
|
積水化学、積水ソーラーフィルム、沖縄電力、ユニチカ 沖縄県宮古島市でフィルム型ペロブスカイト太陽電池の共同実証研究を開始 積水化学工業、積水ソーラーフィルム、沖縄電力、ユニチカの4社は、耐風や塩害など耐候性で過酷な環境である沖縄県宮古島市において防草シートに設置したフィルム型ペロブスカイト太陽電池の共同実証研究を開始した。ユニチカ製防草シート上にフィルム型ペロブスカイト太陽電池を設置。2026年3月までの1年間、沖縄県宮古島市の台風や塩害の影響が大きい地点で耐風および耐塩害の評価を中心に検証する。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月14日
|
|
東大、筑波大、東京科学大 有機半導体における電子相関の発達を観測 東京大学大学院新領域創成科学研究科の竹谷純一教授、筑波大学数理物質系の石井宏幸教授、東京科学大学物質理工学院の岡本敏宏教授らの共同研究グループは、有機半導体に電荷キャリアを高密度に注入していくと、金属転移後、さらに電子相関効果が発達していく様子を確認した。今回の研究では、元々電荷キャリアを持たない単結晶有機半導体にこれまでにない高密度な電荷キャリア(4分子あたり1個の電荷キャリア)を注入することに成功。金属転移後、電子相関効果が発達していく様子を世界で初めて観測した。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月11日
|
|
京大 1次構造が多重制御されたポリビニルアルコールの合成手法を開発 積水化学工業と積水ソーラーフィルムは、香川県協力のもと、フィルム型ペロブスカイト太陽電池を学校体育館の屋根に設置する実証実験を開始した。体育館屋根の南面にフィルム型ペロブスカイト太陽電池を設置し、設置・施工方法、耐久性、発電性能を検証。得られた結果をペロブスカイト太陽電池の設置方法確立へ活かしていく。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月10日
|
|
マクセル 半導体洗浄用途に適した水素ガス発生装置の受注を開始 マクセルは、半導体製造の国際的な業界基準であるSEMI規格に準拠し、EUの安全・健康・環境保護基準適合を示す認証マークであるCEマークを表示した水素ガス発生装置「HGU-36EN」の受注を開始すると発表した。HGU-36ENは①SEMI規格に準拠しCEマークを表示、②欧州RoHS指令に適合した環境配慮製品、③七つのアラーム機能をもつ安全に配慮した機器設計、が特徴。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月8日
|
|
京大 1次構造が多重制御されたポリビニルアルコールの合成手法を開発 京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻の西川剛助教、鈴木宏史博士後期課程学生、大内誠教授のグループは、1次構造が多重制御されたポリビニルアルコール(PVA)の合成手法を開発した。独自に研究してきたホウ素を有するモノマーの分子設計に基づいてラジカル重合における立体規則性を制御し、重合後にホウ素側鎖を水酸基に変換することで立体規則性が制御されたPVAを合成。分子内連鎖移動による分岐生成も抑制可能で、分子量制御や異種ポリマーとのブロックコポリマー化も実現した。これら一次構造を多重に制御したPVAは特徴的な結晶性を示した。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月7日
|
|
東大 対称性の異なる半導体分子による超分子層配列の自己形成を発見 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻の二階堂圭助教、井上悟助教(研究当時)、長谷川達生教授らの研究グループは、アルキル基により対称/非対称に置換した2種の有機半導体分子の混合体を加熱し溶融すると、冷却の過程で液晶相を介して2種の分子がペアを形成する高秩序化が促されることを見出した。この現象を利用し、溶媒を用いずに有機半導体をハイユニフォミティで塗布成膜することに成功した。棒状のπ電子骨格の両端をアルキル基で置換した中心対称な分子と、片側のみ置換した非対称な分子を1対1の比で混合すると、加熱による液晶化や層状化が起こりやすくなることを発見。また、その仕組みは2種の分子がペアを作って並ぶことで得られるπ電子骨格層とアルキル層が多重積層した超分子層構造の形成に由来することを見出した。 |
|
FPD/PCB NEWS〜4月3日
|
|
IBMと東京エレクトロン 先端半導体技術の共同研究開発契約を延長 米IBMと東京エレクトロンは、先端半導体技術の共同研究開発に関する契約を延長したと発表した。新たな5年間の契約では、生成AIの時代を支える次世代半導体ノードとアーキテクチャーの技術の継続的な進展に注力する。 |

